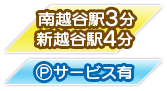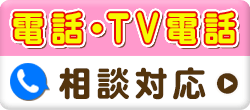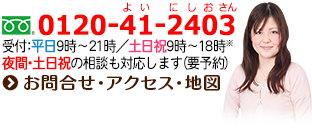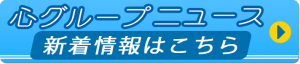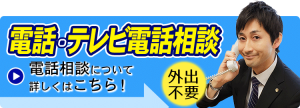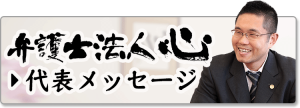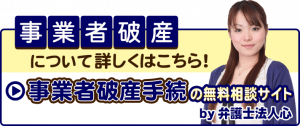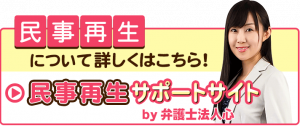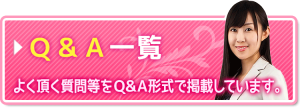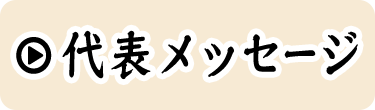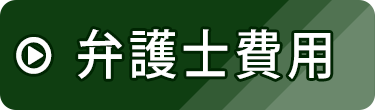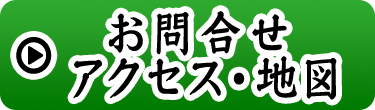債務超過とは|赤字との違い、解消法など解説
「債務超過」という言葉を見聞きしたことがある方もいらしゃると思います。
「債務超過=倒産」というイメージがあるかもしれません。
しかし、本来的には、債務超過は「倒産」や「赤字」という意味ではありません。
以下、債務超過の意味と、債務超過になった場合の解決策について説明します。
1 債務超過とは何か
⑴ 債務超過の意味
債務超過とは、合名会社・合資会社を除く法人の破産原因のひとつであり、債務者である法人が、その債務につき、その法人の全財産をもっても完済することができない状態を意味します(破産法16条第1項)。
破産原因とは、裁判所が破産手続の開始を決定するための条件です。
法人は、後述する「支払不能」に加え、このような債務超過も破産原因となる点が自然人の場合と異なります。
法人は、その資産だけが信用の基礎なので、債務超過の状態に陥った際には早めに破産手続きを開始できるようにして、債権者を保護しているのです。
⑵ 支払不能や赤字との違い
「債務超過」と似たような言葉に、「支払不能」と「赤字」があります。
支払不能とは何か
支払不能は、法人、自然人に共通する破産原因であり(破産法15条1項)、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定義されます(破産法2条11項)。
「支払能力を欠く」とはどのような状態か
これは「債務者の財産、信用、労務をフル活用しても債務を支払えない状態」のことです。
例えば、債務者本人に財産がなくても、債務者本人の信用を使って資金を調達できるのであれば、支払能力があることになります。
あるいは労働能力があり、働いてお金を返せるのであれば、やはり支払能力が認められます。
逆に財産があっても、換価が困難であれば、支払能力はないとされています。
「債務のうち弁済期にあるもの」とは何か
支払わなければならない状態の債務のことです。
期限がまだ先の債務については、将来的に支払える見込みがない状態であっても、期限が到来していない以上、支払不能ではありません。
ただし、債務者が債務の「支払停止」をしたときは、支払不能と推定されます(破産法15条2項)から、反証のない限り、裁判所は破産開始決定をすることになります。
「一般的かつ継続的に債務を弁済できない」とはどのような状態か
「一般的」とは、債務の全部または大部分が弁済できない状態です。特定の債務のみ弁済できている場合でも、総債務の弁済について債務者の資力が不足しているなら、一般的に弁済をできない状態と言えますし、逆に、たまたま特定の債務について弁済ができなくとも、それが全体的な資力不足によるものでなければ、一般的に弁済をできない状態とは言えません。
「継続的」とは、一時的に支払いができない状態を除外する趣旨です。
たまたま資金繰りが悪くて期限までに弁済できなかったけれど、近日中に入金の見込みがあり、そのお金で弁済できるような場合は、支払不能とは認められません。
赤字とはどのような状態か
赤字とは、支出が収入より多いことを指す一般的な用語です。
法律用語ではなく、厳密な定義はありませんが、「今月は赤字だった」「2年連続赤字だった」などのように、期間を限定して使われることが多いです。
設備投資などで支出が増えた結果、その期間だけ一時的に赤字になった場合のように、一定期間だけの話であれば、経営状態としては不健全ではありません。
2 債務超過の解決方法
「債務超過=支払不能」ではありません。
例えば開業資金のためにお金を借りて、事業を始めたばかりの状態であれば、負債の方が資産より大きくなっているケースもあります。
これは債務超過に該当しますが、経営を続けて利益を増やし、その利益で債務が弁済できているならば支払不能とは言えません。
ま た、こうして負債を減らしていけば、債務超過の状態は少しずつ解消されていきます。
キャッシュフローさえ確保できていれば、債務超過でも問題はないということになります。
逆に、帳簿上は債務超過状態でなくとも、資産の多くが換金困難なものであったり、保有している債権の回収期間が長いという理由からキャッシュフローが悪化した結果、運転資金が底をつき支払不能となるケースあります。
赤字でないのに倒産してしまう、いわゆる黒字倒産と呼ばれるものです。
次に、キャッシュフローが好転しない場合の債務超過状態の解決方法について説明します。
⑴ 増資する
会社の資産を増やせば、債務超過の状態が解消されます。
原則的な会社資産を増やす方法は、新株発行による「増資」です。
株主に新株を割り当て出資してもらう株主割当による増資、株主以外の特定の第三者に新株を引き受けてもらう第三者割当による増資、不特定の者に向けて引受けを募集する公募による増資があります。
もっとも、新株の発行は会社の支配権に影響しますので、無議決権株式を発行するなど、弁護士と相談して慎重に方法を選択するべきであると考えられます。
⑵ 債務の免除を交渉する
負債を減らす方法のひとつに「債権者と交渉して債務を免除してもらう」というものがあります。
債権者に債権を放棄してもらうということです。
この方法は債権者に大きな負担が発生しますので、よほどの状況でないと成立しない可能性があります。
債権者が身内などであれば、比較的話し合いがしやすいかもしれません。
なお、債務免除は「利益を得た」もの(債務消滅益と呼びます)として扱われ、課税対象となります。
税金対策も同時に考えなければなりません。
⑶ DESをする
これは「デット・エクイティ・スワップ」の略称です。
「デス」などと呼ばれます。
Debtは債務、Equityは株式という意味です。
債務と株式をSwap(交換)するのが、DESです。
日本語に訳すと「債務の株式化」となります。
銀行などの金融機関が、経営に苦しむ取引先の経営再建をサポートする目的で行われます。
債権者である金融機関が、債権という財産を「出資(現物出資)」し、債務者である債務超過状態の企業の株式を取得します。
企業側は債権という資産を取得しますが、これは自己を債務者とする債権です。
債権者と債務者が同一人に帰属した場合は、債権債務は消滅します(「混同」と呼びます)。
つまり債務がなくなります。
債務者側から見れば、利息が発生する借入金がなくなり、かつ出資を得て資産が増加したと扱うことができます。
債権者側から見れば、回収困難で放棄せざるを得ない可能性のあった債権を、株式という財産に代えることができ、金融機関自体の財産を減らさなくて済むうえ、債務者の株主として経営に関与できることになります。
また経営再建が成功すれば、取得した株式の価値が上がる可能性もあります。
【メリットだけでなく、デメリットもある】
金融機関としては、会社の再建が成功するかは不確実なことですので、再建の失敗によって保有する株価が下がる可能性もあります。
破産した場合、株式は無価値になり、債権回収に失敗したのと同じ状況になります。
債務者側の会社としては、資本金が増加したことにより法人税が増額されるリスクがあります。
また、出資された債権は、もともとは回収の可能性が乏しく、実質的な資産としての価値は債権の名目金額を下回っていたはずです。
つまり、債権の名目金額よりも実質的に低額な資産での出資に過ぎなかったにもかかわらず、名目金額に相応する債務を消滅させるという利益を得られたことになるので、その差額は利益として課税対象と判断される可能性があります。
これも前述の「債務消滅益」のひとつです。
双方にリスクがあるため、慎重な検討が必要な方法です。
⑷ 法人破産を利用する
債務超過を解決できず、その事業には見切りをつけざる得ない場合には、会社の存続は諦めて破産手続きを選択することになります。
法人破産をすると会社の資産は処分・換価されて債権者への配当となり、会社は消滅しますが、残債務もゼロになり、債務超過の状態は解消されます。
なお、会社を消滅させるのではなく、裁判所に申立て、債務を大きく減額したうえ分割弁済を行っていく「再生計画」を裁判所に認可してもらい、その計画に則って、経営を続けながら、会社の再建を進めていく民事再生手続きもあります。
また、もっぱら大規模な株式会社の再建を想定した会社更生手続では、経営陣を全員変え、裁判所が選任した更正管財人によって会社の再建が進められます。
3 債務超過で不安な場合は弁護士へ
債務超過は、必ずしも倒産に直結するというものではありません。
しかし、倒産につながる可能性があることは事実ですので、解消するに越したことはありません。
債務超過が解消できない、または解消の見通しがないなどの場合は、早めに弁護士にご相談ください。
早い段階で弁護士に相談することで、会社を再建できる方法が見つかることがあります。
また、破産をするしかない場合でも、弁護士が手続きをサポートいたします。
自力で破産の手続を進めることは、事実上困難ですので、ぜひ弁護士にお任せください。
当法人には、経営に関するお悩みを解決してきた実績がありますので、ご安心してご相談ください。